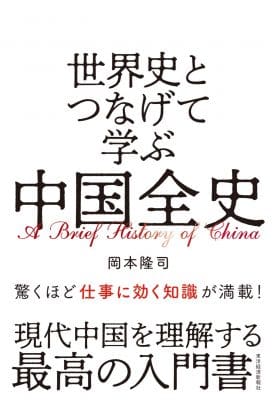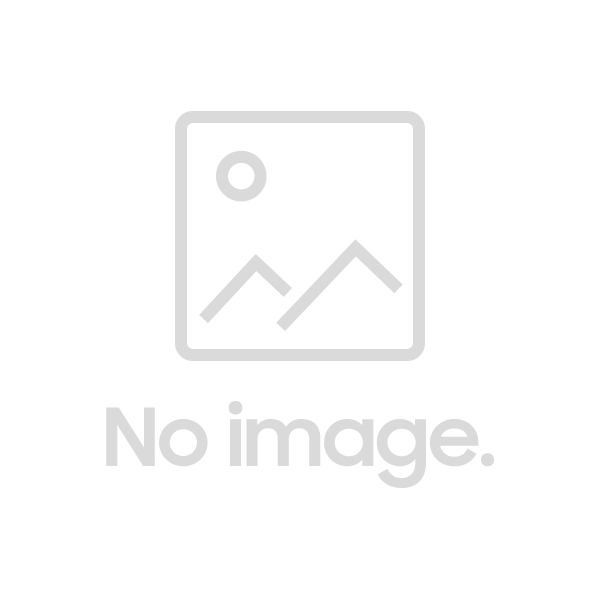中華自民共和国も「中国」の一部である
世界史の一部として「中国史」を学んだあと現代の中華自民共和国を見ると、どうにも繋がらない、違和感を感じます。清までの皇帝をトップに据える統治機構と共産党の違いかなと思っていたのですが、本書を通して歴史的な流れで見るとと中華自民共和国のやっていることは「バラバラになりそうな国をいかに上手くパッキングするかに腐心する」という点で、おおよそ明の時代に始まった「小さな政府」の系譜に連なることで、立て付けは共産主義になって見映えが変わっているけれど、現実的には繋がっているということがよくわかります。中央政府が中央集権的に見えるのはあくまで見映えだけで、実際は地方の権限が大きいんですよね。それをまとめるために中央政府を強く見せる必要がある。日本って基本的に第2次世界大戦を境に断絶していると思うんですよ。今の僕らの中には戦前の日本人のメンタリティというのはあまり残っていなくて、戦後のGHQや高揚する左派政党の形作ってきたメンタリティがとても色濃いと思うんです。少しでも愛国的精神が見られると「右翼」と罵られることがその証拠の1つだと思うんですけど(本来、左派右派問わず愛国的精神というのはベースにあるものだと思うんですけどね)、まあその是非はともかくとして、僕ら日本人は第2次世界大戦で世界が変わったように感じている、その影響でなぜか中国に対してもそんな気がしていると思うんですよ。歴史の中の中国と中華自民共和国とは別物なんじゃないかと。
でも実際の中国は第2次世界大戦で影響を受けたと言っても限定的で、欧米日帝国列強による分割を経てさえ「中国」というものは変わらずに維持され、国内に分断を抱えながらそれを大きく包んで国を維持するという発想では、明の時代かもう600年ぐらい変わっていない。チベットやウイグルに対する倫理を超越した過度な同化政策も、その維持が「中国」そのものの維持に直結しているのだということを理解するとすると、賛同出来るかどうかは別として、その意図自体は理解出来ます。もしそこの独立を認めてしまうと、漢民族の中の違いすらも表面化してしまいかねないんですね。沿岸部と内陸部とか、北部と南部とか。
多民族国家として、また同一民族であっても地域による役割分担(それに基づく地域格差)を基本として、国を形作ってきたのが元以降の「中国」でありそれが現代まで綿々と続いている。
目からウロコがボロボロと
歴史の流れを積み重ねてその結論に辿り着いたとき、正直、膝を打ちました。目からウロコがボロボロと。なるほど、そうだったのか。だから中華自民共和国はあんな感じなんだ。だからこそ統制出来ているようで出来ていない、危うい感じなんだ。だから政府があんなに強硬姿勢なのに民間は自由に商売やってるんだ。中国史と繋げて現代の「中国」を見ることでそういったことがスッと入って来てとても気持ち良くなりました。なるほどね!中国と仲良くしろとか中国人とはこう付き合えとか中国人を理解しろとか、本書はそういったことは主張しません。歴史的に中国と世界および気候変動の関係、中国の統治のされ方と経済、政権の意向の仕方はこうだった、現代でもこうであるそういった古代史・近代史・現代史を貫く「中国」とは何か、そのモデルを本書は提示してくれます。現代の「中国」の未来までは予見出来ませんが、少なくとも中国が必死になって何かをやるその理屈は理解出来るようになる。
そういう意味では、帯に書かれた文句は誇大ではありませんでしたね。中国史の復習であり、かつ、現代「中国」の解説本でもあります。「中国」の枠組みを理解する上で非常にわかりやすく、応用の利く一冊ではないかと思います。おすすめ。