【Tumblr Posts】 Tumblr 2012年10月まとめ 【猫】
 2012年10月にTumblrでPostまたはReblogした画像のまとめ猫編。
2012年10月にTumblrでPostまたはReblogした画像のまとめ猫編。
 2012年10月にTumblrでPostまたはReblogした画像のまとめ猫編。
2012年10月にTumblrでPostまたはReblogした画像のまとめ猫編。
田中ロミオさん原作のライトノベル/SF「人類は衰退しました」のコミカライズ。ただし通常のコミカライズと違って原作を忠実にコミックにしていくのではなく、「設定だけ使ってオリジナル話をやってもらうのはどうでしょう?」(あとがきより田中ロミオさん)というコミカライズ。だからストーリーは新作だし、祖父、わたし、妖精さんの雰囲気も原作とは少しずつ違っています。イラストの雰囲気、センスも原作の挿絵(戸部淑さん)ともアニメとも違っているので(特に妖精さん)、一番最初は少しんん?と思いましたがすぐに馴染みました。むしろこれもありかも。 原作ではなく、かといって原作を壊すことなく、サブタイトルに「のんびりした報告」とあるとおり全体的にはっきりとしたストーリーがあると言うこともなく、下手になぞるよりもこうした「解釈」の方がよほど原作に近い気がします。特に原作を読んでいる人であれば、絵柄の違いが不思議に思えるくらい自然に読めるはず。サブストーリー的な感じで。素敵。 帯で田中ロミオさんが「この一冊で終わってしまうのが惜しまれます。」と書かれてますが続編…ないの?Wikipediaを見る限り挿絵、コミカライズ共にいろいろと紆余曲折があったみたいだけど、そうかー。 人類は衰退しました – Wikipedia 吉祥寺笑さんのコミカライズの方は今も連載続いてるけど(そちらは本当に原作のコミカライズ)、見富拓哉さんの方はこれで終わりなのね。月刊IKKIの連載も今はしてないみたいだし…残念。もし機会があったら続編も読みたいなあ。だめですかー。そですかー。 ともあれ、そんな「残念」に思うほどの素敵な1冊でした。 原作読んだ人、アニメ見た人は是非読むべき。
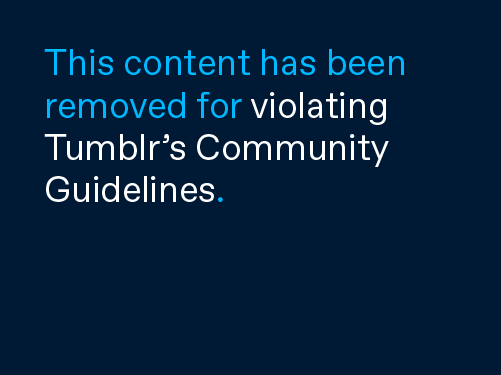 2012年10月にTumblrでPostまたはReblogした画像のまとめ犬編。
2012年10月にTumblrでPostまたはReblogした画像のまとめ犬編。
相方のPCが終了時にエラーウィンドウを出すようになってしまいました。それも1つではなくて複数。 「OK」を押せば問題なく終了させられるものの、「シャットダウン」を押してすぐに終了できないのはそこはかとなく不便。ということでいろいろ調べて試してなんとか直ったっぽいのでやったことまとめ。 (ウィルスではないことは事前に確認済み)
古い友人と久々に再会した場合、同窓会とかでたくさん人がいる中でちょっと会話するくらいだったら違和感を感じないのですけど、ある程度深いところまで知るとなると自分が知っていた友人とは全く違う姿が見えて驚くことがあります。いや、小学校以来って20年以上ぶりなんだから自分の記憶の中の友人と結び付かなくったってなんの不思議もないのですけど、やっぱねそういうのあるじゃないですか。会わない間は進まない時計、みたいな感覚。 僕が小学校、中学校の頃というとバンドブームが終わり頃で、学年の突っ張ったヤツがバンド組んで盛り上がったりしてたもんですけど、そういうのは実際にバンドを組んでいたヤツ以外にも結構影響をもたらすもので、後年になってバンドを組んで活動してるって人が結構たくさんいます。もちろん殆どはアマチュアですが、セミプロ的な人もいたりとか。その中の1人がタイトルのようなことをがっつりmixiの日記かなんかに書いてて、色んな意味でクラクラしたのでした。 まず1つ目、その友人が小学校時代はとても大人しい友人だったのですね。気弱とか物静かとかそう言うのとは違って、どちらかというと優等生側にいるような感じ。常に生徒会に入ってるとかそういう系統の。常に良識があり明るくまっすぐな感じの印象を持っていたので、久々に見たテキストがそれであれこんなやつだったっけと。 次に2つ目、「今どきの若者は」的なおっさんの痛さ。確かに僕らの年代では「アニメをきっかけに音楽を始める」なんて事はなかったです。人間的にどうこうじゃなく、そもそもそういうアニメが存在してなかったですからね。その代わりに僕らにはちょっと有名になったバンドとかアイドルとかが存在してました。ああ、楽器弾いて人前で演奏するのって格好いいなあという感覚。自分もちょっとやったらやれそうな感覚。形式が違うだけで音楽を始めるのに必要な、音楽の素晴らしさや演奏の楽しさは同じように含まれてるわけです。偶像崇拝的な意味も。それを立て付けが違うだけで「きもい」と描写してしまう感受性の低さ。自己認識力の低さ。 最後に3つ目、自身の感情を超えた他人に強制する嫌悪感を公に書いてしまうと言う見識。「けいおん!でバンドブームとかやめてほしい、おたくキモい」と思うのは勝手ですよ。それは止められないですし。だけど、その思いからバンドを組むのは止めろに結び付く過程がよく解らない。それは単純に傲慢なのでは?キミはどんな立派な理由があってバンド活動をしているの?きっかけはどうあれ、音楽が好きで演奏することが歌うことが好きなんだったら、自由にバンド活動をすれば良いじゃない。大体、他人がどんなきっかけでバンド活動を始めるかなんかどうでも良いことじゃないか。 僕自身が「けいおん!」が好きだというのも、僕がその友人の日記に嫌悪感を抱いた理由ではあるけれど、仮に方向性として「けいおん!」のどこが音楽漫画なんだよとか、「ガールズバンドならともかくお前ら関係ないだろ」とか、だったらまだ解るのですけどね。だって認めざるを得ないし。だけど「サブカルチャー」に属するものが「メジャー」に影響を与えた、その結果に対して「オタクきもい」としか反応できないヤツはやっぱり脳の退化が始まってると思うのですよね。 それで嫌悪感を抱いてそれ以来その友人の日記は見ていませんが、今もドヤ顔で書いてるんでしょうかね。と気になって見てみたら8月までで更新は止まっててときおりバンド活動の報告があって、日々の生活のリフレッシュになってたり「バンドの方向性」について悩んでたり、自分の好みの音楽について考えてたり、なにやら楽しそう。ああ、キミが解ってないだけで、僕らの20個下の子達も、同じように好きな音楽に足を踏み入れたんだよ。「アニメがきっかけで」なんていう立て付けを気にしてそんな子達の喜びに目を向けられないのは不幸なことだと思う。音楽は楽しいんだよ。知ってるだろ?
先日windows7でガジェットの代わりになるオシャレなデスクトップ時計、 「MoonyDesk」を紹介しました。 【Windows 7】 デスクトップに表示するシンプルでオシャレな時計MoonyDesk(と、表記のカスタマイズ) | mutter この中で、日時表示の並びが日本式だと微妙だから、Windowsの日付形式をいじって対応させようぜという話を書いたのですが、その状態で使っていてちょっと不便な点があったのでその報告と調整方法について。
 本日、Firefoxが17になったみたいです。
で、アドオンの「Tab Mix Plus」がまだ対応していなくて無効になり、新しいウィンドウで開いてしまったり、ブックマークが同じタブで開いてしまったりしているようで。この辺のアドオンの問題はなかなか上手い手が見つからないですなあ。
解決方法としては、強引に有効にする方法もあるのですが、今回についてはFirefox17に対応した「Tab Mix Plus」のプレリリース版がリリースされているので、それを入れれば吉かと。下のリンク先の最初の書き込みの「Dev-Build」をクリックすればOK。
Tab Mix Plus Dev-Build 0.4.X • Tab Mix Plus
次のような警告が出たら「許可」をクリック。
本日、Firefoxが17になったみたいです。
で、アドオンの「Tab Mix Plus」がまだ対応していなくて無効になり、新しいウィンドウで開いてしまったり、ブックマークが同じタブで開いてしまったりしているようで。この辺のアドオンの問題はなかなか上手い手が見つからないですなあ。
解決方法としては、強引に有効にする方法もあるのですが、今回についてはFirefox17に対応した「Tab Mix Plus」のプレリリース版がリリースされているので、それを入れれば吉かと。下のリンク先の最初の書き込みの「Dev-Build」をクリックすればOK。
Tab Mix Plus Dev-Build 0.4.X • Tab Mix Plus
次のような警告が出たら「許可」をクリック。
 しばらく待てば正式版としてもリリースされると思いますが、待てないという方はどうぞ。
今のところ大きな問題は出ていないようなので、多分大丈夫です。保証は出来ませんが。
しばらく待てば正式版としてもリリースされると思いますが、待てないという方はどうぞ。
今のところ大きな問題は出ていないようなので、多分大丈夫です。保証は出来ませんが。
 なんとなく見掛けたフレーズに絡んでいくシリーズ。
特定の相手がいるわけじゃありませんけども。
なんとなく見掛けたフレーズに絡んでいくシリーズ。
特定の相手がいるわけじゃありませんけども。
ネットは公平な場所であり、実名であろうと匿名であろうとHNであろうと同様に1つのユーザーであり、そういう場所では言葉の本質的な力が強調される。すなわち「誰が言ったかでは無くて何を言ったか」が重要なのであり、発言者の氏素性によってフィルターを掛けるのではなくその発言内容に真摯に向き合うべきである……馬鹿言えと思います。 もっというと、馬鹿も休み休み言えと。
追記:調子よく書いては見たものの、地域と言語で形式を変更するとシステム全体の日付形式が変わってしまってちょっと使いづらいですね。うーむ。
追記(その2):なんとなく対策考えてみました 【追記】 デスクトップ時計MoonyDeskの日時表記をオシャレにしつつ支障の少ない日時設定Windows7でデスクトップ上に時計を表示させるというとガジェットなんですが、どうやらガジェットにはセキュリティ上の問題があるらしく、配布用のサービスを閉鎖するなどMicrosoftもサポートを打ち切っていて使えません。残念。 Windowsの「サイドバーとガジェット」に脆弱性、機能無効化ツールを公開 – ITmedia ニュース Windows 7のガジェット機能に攻撃のおそれ――8では「廃止」か | セキュリティ・マネジメント | トピックス | Computerworld – エンタープライズITの総合ニュースサイト 何か代わりになるものは無いかと思って探していたところ、こんなツールを見つけました。 MoonyDesk (windows desktop widgets) – Home デザインが格好良く機能もシンプルで良かったので採用。 天気予報は別に要らなかったので機能を時計だけに絞って右下に表示してこんな感じ。
 良い感じ。
時計を置きたいけど気合い入れてカスタマイズまではしたくない、という方にオススメです。
良い感じ。
時計を置きたいけど気合い入れてカスタマイズまではしたくない、という方にオススメです。
「正圧」と「負圧」という概念があります。