タグ: 仕事
今日の佐川急便さん
prrr ガチャ ―― はい 「○○さんのお宅ですか」 ―― ええ、そうですが 「あーえーと佐川急便ですけれども」 ―― はい 「○○様宛のお荷物がですね、20時から21時の時間指定いただいてるんですけれども、その時間に行けないんですよ」 ―― は?
サマータイムも良し悪し
先日書いたとおり、今の勤務時間は1人サマータイムになってるんですけど、僕の場合元々が10時半始業と遅めだったので、1時間半早まったところで世間とズレた感はないかな…というか、むしろ社会にようやく適合できたような感じ。帰る時間が早くて仕事が終わってからも店がまだ営業してるし。朝起きるのは苦にならないし、かといって深夜の活動も縮小されてないし、非常に快適です。夏の節電対策で、関西に事業所を置く企業でも相次いで導入している「サマータイム」。就業時間を早めることで余暇を有効活用できるメリットが生まれている半面、社員の生活サイクルを乱し、仕事量がかえって増えるというデメリットも出てきているようだ。 (中略) ただ、サマータイムを取引先が導入していないケースも多く、勤務時間や休日を取引先に合わせる必要もある。6月からサマータイムを導入した住友金属工業の大阪本社で自動車メーカーを担当する営業部門の男性社員(43)は、自動車業界が一斉休業している木・金曜を休み、土・日曜に出勤している。「サマータイムで早く帰れると思ったが、土・日曜に子供と過ごす時間が減った」と残念そうだ。 今月からサマータイム導入で始業時間が45分早い8時となった食品メーカーでは、大阪支社に勤める男性社員(40)が「問屋の都合に合わせ、夕方以降まで働くのは以前と変わらない。睡眠時間が減り、仕事量がかえって増えた」と嘆き、通勤時間が1時間という東京本社の営業担当の男性(35)も「3歳の息子を預ける地元の保育園が開くのは7時半なので、交代でしていた送り迎えはほとんど妻に任せっきりになった」と戸惑いを隠せない。
人によって能力には違いがある – 誰もが大局観や自走能力を持てばいいわけではない
最近「人には最適な働き場所がある」ということをずっと考えていて、 何度か文章に起こそうとしてみたのだけどなかなか上手くいかん。 自分が知っている範囲が狭いからなぁ… しかしまぁ、それでも考えていることをメモして残しておきたいので箇条書き。
- 「自ら考えて動く社員こそが至高」というのは幻想
- ルーチンワークや事務作業は必ず必要でそれ専門の人員も必要
- 管理業務は事務作業の上位種ではなくて全然別部門、求められる技能も当然別
- 責任範囲の判断は本人ではなくその上位の管理者がすべき
1人サマータイム
 7/16から出勤時間を1時間半早くして出勤しています。
タイトルにはそう書いたけど別にサマータイムだとかいうつもりではなくて単純に、
7/16から出勤時間を1時間半早くして出勤しています。
タイトルにはそう書いたけど別にサマータイムだとかいうつもりではなくて単純に、
- 朝早く仕事を始める方が夜遅くまでやるより集中できる
- 同じ時間働くなら早く帰宅できた方が得した気がする
- 家でエアコン付けないから暑い
JRAでバイトしてたときの食堂禁止令の話
職場にて他店に送付するPCのセッティングをしてるんだけど全然終わらなくて、 かといって業務にも入れないので思い出話でも書く。 * * * 大学時代に部活の縁でJRAのバイトをよくしてました。 競馬場の整理とかそんなんじゃなく、厩舎で競馬運営の手伝いをするバイト。 パドックに向かう1時間半前くらいから1時間、準備をしている馬の前に座って、 薬物投与などの不正がないか監視する仕事です。 基本、何かツテがない限り普通の人は従事できない系のバイトですね。責任もあるし。 給料は結構良かったと思う。 まぁ全部部活の予算に回るのであんまり関係のない話ですけど。
営業の人の作り笑いが苦手で
仕方がないことだとは思うんですけどね… 営業に従事してる人全員がそうというわけでは全くないんですが、 一定の割合で笑いが全て乾いている人というのがいますよね。アレが苦手で。 本人は別に悪気はなくて雰囲気のために一生懸命やってるんだと思うんですけど、 聞いてる方としては、
- 「あー聞いてないなー」
- 「言いたいことあるんだろなー」
今日の失敗: ○○さんですか?
rrrr….
僕 「はい、お電話ありがとうございます。△△です。」
? 「あの、すみません、○○さんですか?」(「○○」はうちの社長)ここで僕、ナチュラルに、
僕 「いえ… 違いますが…」いや、違うのは正しいんだけど、いちおう解るよね… 「今、○○は席を外しておりまして」などと言えば良かったんだけど、なぜか、そう言ってしまったんだよ、 んで、先方も聞き返してくれればいいのに、
? 「あ、すみません…」ガチャッ、ツーツーツー …。 結局先方が誰でなんの用だったかは皆目分からず。 いや普通に考えて取引先だよね… …。 うん、まぁ、仕方ないよね…
顧客の要望をどこまで聞くべきか? 【小ネタ】
 そうだろうなぁ。そうだと思うよ。
自動車が出てきたときの「鍛冶屋の逸話」という有名なたとえ話があるのだけど、その辺の話かな。
そうだろうなぁ。そうだと思うよ。
自動車が出てきたときの「鍛冶屋の逸話」という有名なたとえ話があるのだけど、その辺の話かな。
「自動車」と言うものが世に出てて来たとき、世の中の一般的な乗り物は馬車であり、馬の蹄鉄を打っていた鍛冶屋は皆、「あんなものが役に立つか」と嗤っていたのだけど、その後自動車は馬車に変わって普及していき、結果的に鍛冶屋の殆どは職を失ったもちろん「顧客の要望を聞くべきではない」という話ではなくて、今あるものの延長線上でちょっと良くするという話であれば当然顧客の要望を聞くと言うことは効果絶大なのだけれど、何でもかんでもそれで上手く行くかというとそうでもないから、その辺バランスを考えながら上手いことやっていかないとダメだよね的な。 上手く行かないときに、
- 要望を拾い上げる
- → 要望に応えようと様々な改善案を実施する
- → 目的がぼやけて迷走する
- → 要望に応えようと様々な改善案を実施する
引用元:
Startup Quote 日本版「ググレカス」の穏当な表現が欲しいんだ
堀江さんのブログから。
たまにネット上で聞く言葉「ググれカス」。検索すれば一発でわかるのに、知らない事をtwitterとか掲示板とかで質問してくる人に良く言われる言葉である。とりあえずgoogleで検索しとけよ(ググれ)ってことである。 しかし、こんな感じの人は一般社会にも多い。私は先日とあるテレビ番組に出演した時に、番組収録中に出て来たキーワード、わからないことをiPhoneで検索して即座に示したらびっくりされ、ある意味呆れられた。でも、今や検索エンジンは持ち歩ける時代になっているわけだし、わからない事があったら即座に検索すればわかるのである(電波さえ入っていれば)。 やらないのとやるのでは大きな差がでてくる。
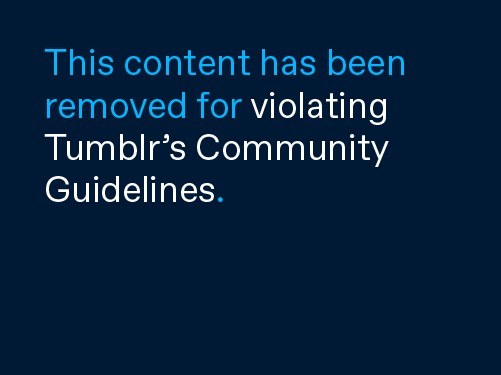
 Business Media 誠:「サマータイム」メリットもあるが……「仕事量増えた」の声も
Business Media 誠:「サマータイム」メリットもあるが……「仕事量増えた」の声も