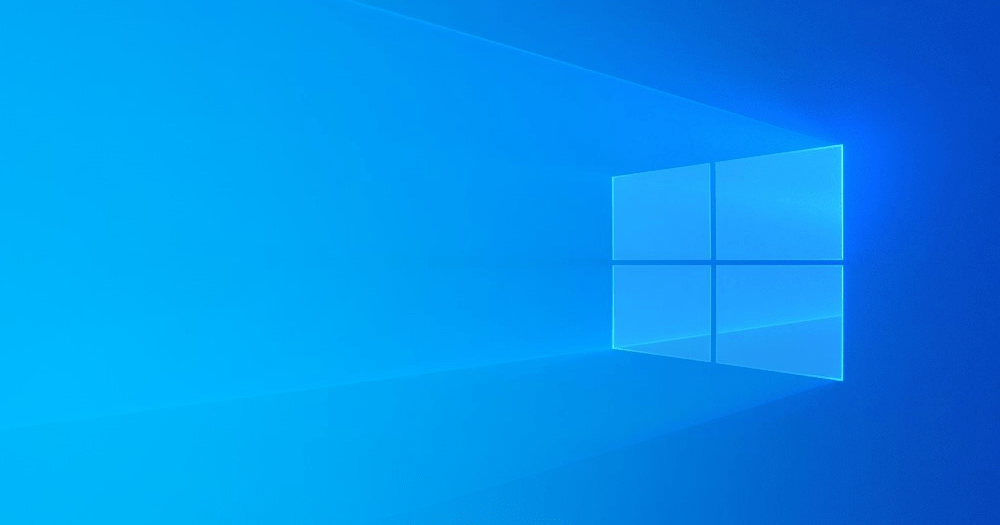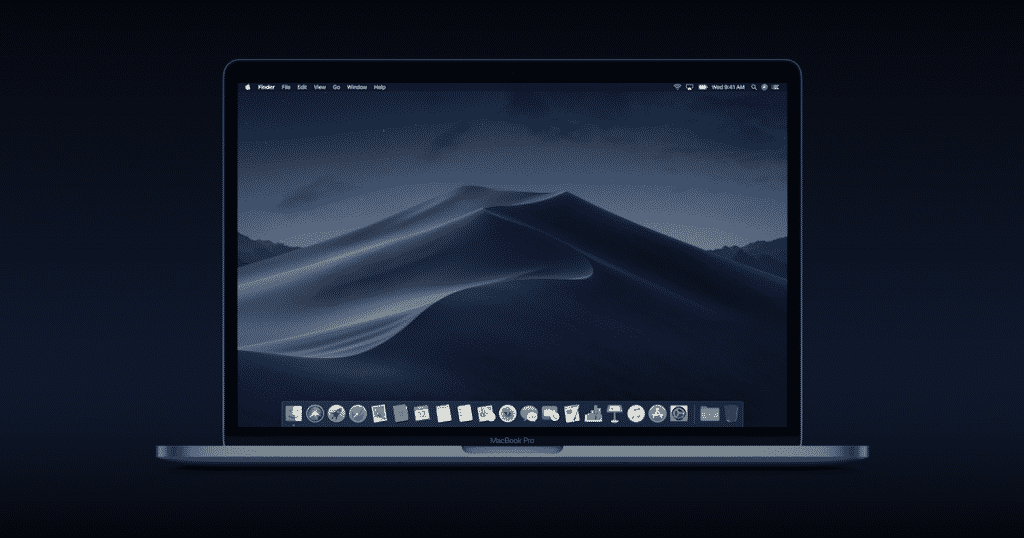カテゴリー: Mutter
【京都マラソン2019】「42.195km 走りきれるのか」という不安との戦い
【メモ】Windowsでアンインストールが出来ない時に確認すること
サイトリニューアルの話がなんだか大掛かりになってきてる【#np2020】
 ※リニューアルあるあるです
少し前に サイトのリニューアルをしようかな という話を書きまして、ローカルでBootstrapでテンプレート作ったり、SSLに対応させたり してたんですが、その過程で重要度の低いサイトから順に、GitHubと連携させつつsvnからgitに移行としようとしていて衝撃が。サーバのOSが古すぎて最新版のOpenSSLが入らず、GitHubと連携できない。マジで。
使っているOSはCentOS5.6で確かに古い。今のサーバ(さくらのVPS)を契約した時点で既に大分枯れていたと思うんだけど、使い慣れてるからって言う理由で選択したんだよね。個人サイトの環境なんだからもっと冒険しておけば良かった。
ここでGitHubを諦めるという選択肢ももちろんあるんですけど、仮にサーバが止まっても収入がなくなるわけでも責任問題になるわけでもなし、じゃあもこの際サーバを引っ越しましょうかということに。なんでそうなる。
※リニューアルあるあるです
少し前に サイトのリニューアルをしようかな という話を書きまして、ローカルでBootstrapでテンプレート作ったり、SSLに対応させたり してたんですが、その過程で重要度の低いサイトから順に、GitHubと連携させつつsvnからgitに移行としようとしていて衝撃が。サーバのOSが古すぎて最新版のOpenSSLが入らず、GitHubと連携できない。マジで。
使っているOSはCentOS5.6で確かに古い。今のサーバ(さくらのVPS)を契約した時点で既に大分枯れていたと思うんだけど、使い慣れてるからって言う理由で選択したんだよね。個人サイトの環境なんだからもっと冒険しておけば良かった。
ここでGitHubを諦めるという選択肢ももちろんあるんですけど、仮にサーバが止まっても収入がなくなるわけでも責任問題になるわけでもなし、じゃあもこの際サーバを引っ越しましょうかということに。なんでそうなる。
引用記事内に掲載しているWebサイトのサムネイルを「HeartRails Capture」から「blinky」に変更しました。
【今日のニュースから】ハナタレナックス:特番が5年連続で全国放送 大泉洋らが札幌ですごろくツアー 安田顕が「獅子奮迅」?
全国放送があるってのはHTBのインスタで見てたんだけど、まさか全国紙で取り上げられるとは…… 今さら改めていうことでもないけど、大きくなったなあ。 下町ロケットのリーダーも好演でしたねー 全国放送版は若干薄味だけど(仕方ない)、紹介見る限り面白そう。楽しみ!ハナタレナックス:特番が5年連続で全国放送 大泉洋らが札幌ですごろくツアー 安田顕が「獅子奮迅」? – 毎日新聞
俳優の大泉洋さんらの演劇ユニット「TEAM NACS(チーム・ナックス)」のメンバー5人が総出演する北海道ローカルのバラエティー番組「ハナタレナックス」(北海道テレビ放送)の特別番組が、5年連続で全国放送されることが25日、明らかになった。「ハナタレナックスEX(特別編) ニッポンが行きたい北海道~ドキドキ!札幌すごろくツアー~」と題して、TEAM NACSの大泉さん、森崎博之さん、安田顕さん、戸次重幸さん、音尾琢真さんら5人の珍道中を放送する。2019年2月10日午後1時55分から。 「ハナタレナックス」は、03年にスタートした北海道ローカルのバラエティー番組。15年から毎年2月に特番が放送されている。特番第5弾となる今回は札幌を舞台に、北海道のグルメや魅惑の観光スポットなどが網羅された「オリジナルすごろく」を使って、5人が2日間のツアーを行う。サイコロの目やルートを決める自分たちの選択により、手が届きそうで届かない行き先もあり、5人は愚痴ったりボヤいたり、時にズルをしたりとTEAM NACSらしい一面を見せつつ、ツアーを敢行。お土産屋さんでカゴを片手に奮闘したり、寒空の下でポージングしてみたりと、全国放送ではなかなか見られないTEAM NACSの“素顔”や“絆”、“小ささ”が盛り込まれた内容になっているという。 ロケ終了後、リーダーの森崎さんは「以前から知ってた店でも、こんなおいしいものがあったんだというのを知ることができました。より深く、わが街、札幌のことを好きになる収録でした!」と撮影を振り返り、安田さんも「(今回の特番は)意外と面白くなってるんじゃないですか? 適度なゆるさがあって」とコメント。今回の見どころについて大泉さんが「見てほしいのは、やっぱり僕たちの『絆』だな、ほんとね。友情というか」「今回のラストは、ほんと、絆よ」と語ると、音尾さんも「最後にあんな感動的なフィナーレをね!」と同意。戸次さんは「獅子奮迅とはこれだって働きを安田がします!」と安田さんの活躍を予告した。
新元号と平成31年
 なんとなく「今月いっぱいで平成は終わり」「平成は30年まで」みたいな機運になってますけど、でも実際に新元号が発表されるのは4月で改元は5月1日ですよね。ということは、来年新元号元年になる前に「平成31年」が4ヶ月間あるわけですよね。7日間しかなかった「昭和64年」ほどではないにしても。
天皇陛下の儀式関連は決まっていることがたくさんあり、軽々に日程を動かしたり出来ないというのはわかるんですけど、なんつうかなー、上手いこと12月31日までで1月1日から新元号!みたいなことには出来なかったんだろうか。もちろん書いてて気付いてるけど、そんなんされたら年末年始に掛けて悲鳴を上げる人がたくさん出て大変なことになるけど、でもまあなんというか、いつ改元になってもそうなるからさ……
と思ったらこんなんあった。
なんとなく「今月いっぱいで平成は終わり」「平成は30年まで」みたいな機運になってますけど、でも実際に新元号が発表されるのは4月で改元は5月1日ですよね。ということは、来年新元号元年になる前に「平成31年」が4ヶ月間あるわけですよね。7日間しかなかった「昭和64年」ほどではないにしても。
天皇陛下の儀式関連は決まっていることがたくさんあり、軽々に日程を動かしたり出来ないというのはわかるんですけど、なんつうかなー、上手いこと12月31日までで1月1日から新元号!みたいなことには出来なかったんだろうか。もちろん書いてて気付いてるけど、そんなんされたら年末年始に掛けて悲鳴を上げる人がたくさん出て大変なことになるけど、でもまあなんというか、いつ改元になってもそうなるからさ……
と思ったらこんなんあった。
あー。そうだったのね。 まあ普通に効率考えたら元日改元でってなるよねえ。 毎年の行事をこのために取りやめるってわけにはいかないのね。そりゃそうか。皇室の仕組み自体、基本的に「退位」というものが要件に含まれてないからなあ。年賀の行事を1週間遅らせて、新天皇が執り行う問ことにすれば良いんじゃないのとも思うけど、そういうわけにもいかないんでしょうね。大変だ。 多分、天皇陛下に伺ったら、柔軟にしていいよといわれるような気がするけれど、天皇陛下のことは天皇陛下が決められるわけではないというのが今の日本だし、色んな人の気持ちもあるだろうし、そういうの無視して効率のことだけ言っても仕方ないか。 というわけで、平成最後の桜も平成最後の花粉症もまだこれからだぞ! まだもうちょっとだけ続くんじゃ(CV: 宮内幸平 as 亀仙人)。政府が推していた「2019年元日改元案」が見送られた背景│NEWSポストセブン
天皇にとっての元日は“1年のうちで最も忙しい日”とされる。早朝から宮中祭祀に臨み、「新年祝賀の儀」では首相や衆参議院議長、最高裁長官をはじめ約700人もの要人と分刻みで面会する。お身内との「御祝御前」も22時まで続くこともある。翌2日の一般参賀の後も行事は続く。1月3日には成人皇族が参列する「元始祭」があり、翌4日には掌典長から前年の祭祀が滞りなく執り行なわれたという報告を受ける「奏事始」がある。昭和天皇の命日である7日には「昭和天皇祭」も控えており、その準備にも追われる。天皇の正月はまさに“息つく暇もない”のである。 (中略) 政府は当初、区切りとして分かりやすいということで、2019年の元日に改元する案を推していました。しかし陛下がご多忙を極められる元日の直前に、退位と即位に関する様々な儀式を行なうのはどう考えても無理。陛下も正月の行事を非常に大切にされていることから、宮内庁から強い反対意見が上がり、元日改元案は見送られたのです
Tumblr 10年
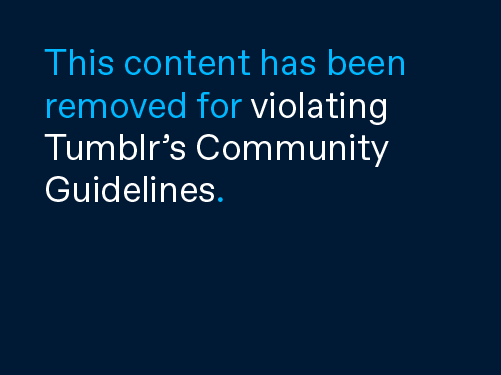 「Tumblr 10年について」的な話をotsuneさんがしてるのを見掛けて、そうなのかーと思って見返してみたら僕がTumblrを始めたのは2008年10月25日のことでした。ちょうど10年前ですね。
Tumblrを始めてみました。(Firefoxで良い拡張を見つけたので) | mutter
この時点で既に「超遅ればせながら」と書いていて、過去のツイートやメールを検索してみるに、僕の周りで盛り上がり始めたのはその前年、2007年の7月くらいなのかなと思われます。Tumblrのサービス開始は2007年3月1日だということなので、Tumblr自体はサービス開始からおよそ11年半、僕が利用するようになってからおおよそ10年てことになるようです。もうそんなに経ちましたか。
Tumblr – Wikipedia
その間に社名が変わり、米Yahoo!に買収され、創業者が辞め、環境も随分変わりましたね。
僕が熱心に使っていたのは2008年から2015年くらいまで。当時からテキストやリンクのリブログも活発に行われていましたが、僕は画像専門で気に入った画像をポストまたはリブログしていくというスタイルでした。マイクロブログと言うよりは画像アーカイブって感じ。中にはアダルトな画像もあったけれど、基本的には美しいものを選んでいたような記憶があります。生々しいのはちょっと。あとは犬とか猫とか自然風景とか。そのためにロシア語わからんのにロシア語サイトを掘ったりとかしてたなあ。
「Tumblr 10年について」的な話をotsuneさんがしてるのを見掛けて、そうなのかーと思って見返してみたら僕がTumblrを始めたのは2008年10月25日のことでした。ちょうど10年前ですね。
Tumblrを始めてみました。(Firefoxで良い拡張を見つけたので) | mutter
この時点で既に「超遅ればせながら」と書いていて、過去のツイートやメールを検索してみるに、僕の周りで盛り上がり始めたのはその前年、2007年の7月くらいなのかなと思われます。Tumblrのサービス開始は2007年3月1日だということなので、Tumblr自体はサービス開始からおよそ11年半、僕が利用するようになってからおおよそ10年てことになるようです。もうそんなに経ちましたか。
Tumblr – Wikipedia
その間に社名が変わり、米Yahoo!に買収され、創業者が辞め、環境も随分変わりましたね。
僕が熱心に使っていたのは2008年から2015年くらいまで。当時からテキストやリンクのリブログも活発に行われていましたが、僕は画像専門で気に入った画像をポストまたはリブログしていくというスタイルでした。マイクロブログと言うよりは画像アーカイブって感じ。中にはアダルトな画像もあったけれど、基本的には美しいものを選んでいたような記憶があります。生々しいのはちょっと。あとは犬とか猫とか自然風景とか。そのためにロシア語わからんのにロシア語サイトを掘ったりとかしてたなあ。
【今日のニュースから】 打首獄門同好会ベースjunkoさん 還暦おめでとうございます
マジで!!!!!! 打首獄門同好会と言えば「どうでしょうバカ」の中ではつとに名前を知られておりますが、しかしまさか還暦だったとは……
この画像は一体(笑)なんやjunkoさん還暦って!
— ヌオー (@nuuhernandez14) 2018年12月20日
俺はずっとこれを信じ込んでたぞ! pic.twitter.com/YDwovrzf5i
そしてjunkoさん超格好いい。格好良すぎる! お誕生日おめでとうございます!!!!!え?ウソでしょ?junkoさん 還暦??めっちゃロック!!! pic.twitter.com/YkGRRKAd2Z
— LOKI (@Lokicat77) 2018年12月20日